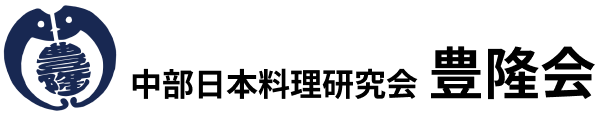かぶの原産地はヨーロッパ。大根よりも渡来は古く、奈良時代には関東で栽培されていたとも。春の七草の一つであるスズナのこと。近江かぶ、温海かぶ、聖護院かぶ、尾張かぶ、赤かぶと地方品種も多い。じっくりと炊いたかぶと一気に炊きあげた鯛。時間差が趣きのある味わいに!
鯛上身 60g×4切、小蕪4玉、千六本人参 20本、蕪の芯芽、あられ柚子、鯛粗、 昆布出汁(水1ℓ、昆布5%=50g)
A:昆布出汁1200cc、石野の白味噌 60g
~、仕上げ酒20cc
1.昆布出汁を取る。容器に分量の水と
昆布をきれいに拭いて入れ、冷蔵庫
で15時間浸して美味しいだしを取
る。浸し時間は味見をして加減する
とよい。
2.鯛粗をぶつ切りにし、2%くらいの
ふり塩をして約30分おいて、熱湯を
回しかけてよく洗う。
3.小蕪は葉茎と根に切り分け、枝の頭
と尻を落として太鼓形にし、.厚めに
皮をむきそのまま使用する。
4.鯛の上身にも2%のふり塩をして約
30分おいて、熱湯を回しかけてよく
洗う。
5.1の昆布水と小蕪を鍋に入れ強火に
かけ、沸いたら弱火にして柔らかく
なるまで約20分ゆでる。ざるに取り
冷ます。
6.3の葉茎は外側の太い茎を取り除
き、芯の柔らかい部分を使用する。
長さを5cmくらいに調え、5のゆで
汁を漉してさっと湯がき、冷水に取
って色出しをする。ゆで汁は取りお
く。
7.6のゆで汁に2の鯛粗を入れ中火にか
け、約15分煮出し布巾で漉す。
8.7の漉しただしを鍋に入れ、5の蕪を
入れて中火にかけ、沸く直前に白味
噌を溶かし弱火にして約5分煮含め
る。
9.4の鯛の上身を8に入れ酒を加え、身
割れがしないよう極弱火で約10分炊
く。
10.千六本に切った人参を下茹でして
おいて、9の煮汁を別鍋に少し取っ
て軽く煮る。6の葉茎も9の煮汁に浸
す。
11.煮物椀に9の鯛と小蕪を形よく盛
り、さっと温めた人参と茎を添え、
あられに切った柚子皮を天盛りにし
て供す。